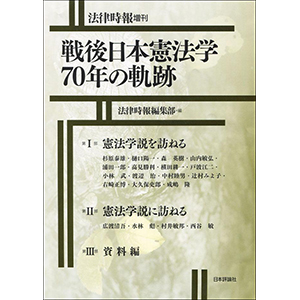法律時報 編集部ブログ 今月の最新記事
◆2025年11月号 「法」的側面から見た租税制度<好評発売中!>
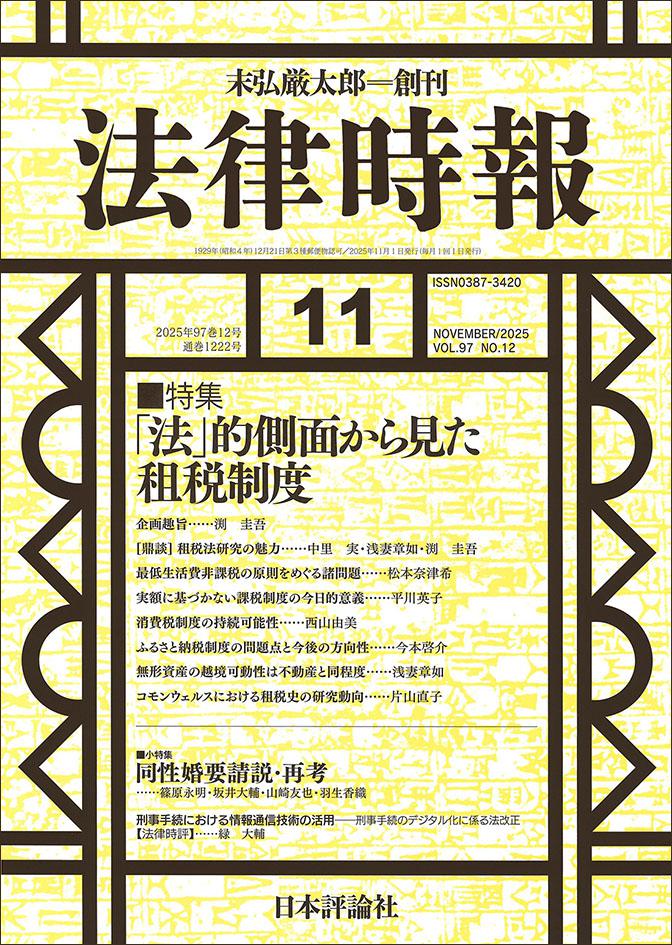
|
企画趣旨近年、国政選挙や主要政党の代表選挙において、租税制度がしばしば争点の一つになっている。とりわけ、租税制度の法的側面に関わるテーマが注目を集めている。やや一般化して言えば、租税政策について、財政立憲主義や平等原則のような憲法上の諸原理及び国際法上の規律管轄権・執行管轄権のような法的観点から語ることの重要性が … (本誌より抜粋/本文内容一部参照できます!) |
——2025年11月号目次——
[鼎談] 租税法研究の魅力 … 中里 実・浅妻章如・渕 圭吾(司会)
最低生活費非課税の原則をめぐる諸問題 … 松本奈津希
実額に基づかない課税制度の今日的意義――フランスの「フォルフェ」について … 平川英子
消費税制度の持続可能性 … 西山由美
ふるさと納税制度の問題点と今後の方向性 … 今本啓介
無形資産の越境可動性は不動産と同程度 … 浅妻章如
コモンウェルスにおける租税史の研究動向 … 片山直子
企画趣旨 … 篠原永明
法典論争延期派の旧民法人事編解釈――穂積八束と奥田義人 … 坂井大輔
憲法24条の「変遷」?――その解釈の限界 … 山崎友也
婚姻と親子関係の連動性 … 羽生香織
同性婚と親子関係法――憲法の観点から … 篠原永明
親族である名義人の承諾に基づくETCカードによる高速道路の利用と電子計算機使用詐欺罪 … 松原芳博
●信用の基礎理論構築に向けて・14-1
近松門左衛門『冥途の飛脚』に見る信用をめぐる社会構造(上) … 桑原朝子
●メタ「法学入門」・13
民法学 その7 … 小粥太郎
●法的判断において「議論」が果たす役割の諸相――法学と議論学との協働・9 [最終回]
コメント――「議論」に関する既存の研究との対比 … 西村友海
●民事法律扶助制度の改革・9
エンパワーメント型の法律扶助の可能性 … 飯田 高
●日本の民主主義・2
SNS時代の日本の選挙運動規制再考 … 上田健介
●憲法と家族法の交錯・11
親権制限における親の権利と子の福祉――児童虐待を中心に … 阿部純一
●行政法学のリ・デザイン――二元的思考を超えて・17-2 [最終回]
国内法と国際法のはざま(下) … 原田大樹
●名誉毀損・侮辱を巡る比較刑法研究・2-3
イギリスにおける名誉保護法制(3・完) … 山田 慧
●拘禁刑時代の施設内処遇・13
刑事収容施設における医療――拘禁刑下処遇における同等性実現に向けた改革への期待と懸念 … 松田亮三
●デジタルプラットフォームと経済法の世界的新展開・2
ランキング表示における自己優遇――AT40703 – Amazon Buy Box[2022] … 瀬領真悟
◆2025年10月号 民事紛争の解決手続と時間<好評発売中!>

|
企画趣旨安全保障に関しては、事実としては起こりうる重大な事態や状況であっても、ある種の願望も込めて、「起こってはならないもの」あるいは「起ぎるはずがないもの」として扱われ、実際にそうした事態が(滅多に)生じなかったことも手伝って、法の整備や学問的検討が不十分なままになっている場合がある。また、自国の安全保障を … (本誌より抜粋/本文内容一部参照できます!) |
——2025年10月号目次——
海上におけるグレーゾーン戦略・ハイブリッド戦への対処と国際法 … 西村 弓
大量破壊兵器のタブー――リアルに対応する制度のリアル … 阿部達也
原子力施設に対する攻撃をどう防ぐか――その防止・防御のための国際法的枠組み … 森川幸一
国連は絶対的機能不全に陥ったのか――設立80年目の危機における国際法上の課題 … 丸山政己
能動的サイバー防御の国際法上の意義と課題 … 酒井啓亘
侵略国の政府資産の凍結と没収の国際法上の評価 … 坂巻静佳
経済安全保障の時代における諜報活動の刑事規制のあり方――ドイツの法的状況を中心に … 久保田 隆
企業による安全保障阻害行為への対処の積極化と限度 … 関根豪政
平和と法をめぐる対話──
「〈戦争を知らない子どもたち〉だけのこの国」を目の前にして
… 山元 一・石川健治・小畑 郁・井上武史・三牧聖子・根岸陽太・江島晶子・横大道 聡
AI生成性的画像を巡る刑事立法学(下)――日台の法比較を中心に … 深町晋也
誤振込と被仕向銀行の刑事責任 … 西村剛輝
NEW●日本の民主主義・1
戦後日本憲法学における「民主主義」理解の変遷 … 新井 誠
NEW●デジタルプラットフォームと経済法の世界的新展開・1
企画趣旨 … 土田和博
アプリストアの競争導入とセキュリティ、プライバシ――Epic Games, Inc. v. Apple, Inc., 67 F. 4th 946 (9th Cir. 2023)を手がかりに … 土田和博
●メタ「法学入門」・12
民法学 その6 … 小粥太郎
●法的判断において「議論」が果たす役割の諸相――法学と議論学との協働・8
コメント 法的判断×議論――交差点から遠ざかる … 大村敦志
●民事法律扶助制度の改革・8
民事法律扶助制度と日弁連が行う法律援助事業の関係及び課題 … 桐本裕子
●憲法と家族法の交錯・10
憲法研究者からみた親子法制の風景 … 稲葉実香
●行政法学のリ・デザイン――二元的思考を超えて・17-1
国内法と国際法のはざま(上) … 原田大樹
●名誉毀損・侮辱を巡る比較刑法研究・2-2
イギリスにおける名誉保護法制(2) … 山田 慧
●拘禁刑時代の施設内処遇・12
拘禁刑下の規律秩序のあり方 … 本庄 武
●公判外供述の比較法研究・4-6
イギリスの刑事手続上の公判外供述(6・完) … 佐藤友幸
◆法律時報増刊
◆判例回顧と展望 2024年度版(法律時報臨時増刊)
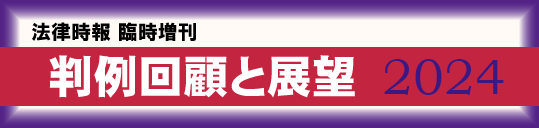
≪2025年6月上旬 発売≫
2022年度に文献掲載された重要判例を法分野別に整理し、その意義と位置づけを簡潔明快にコメント。毎年好評の判例特集号最新版。
—— 目次 ——
憲法 /金澤 誠・黒澤修一郎・横堀あき・内藤 陽・大串倫一・齊藤正彰
行政法/佐伯彰洋・小川一茂・重本達哉・近藤卓也
刑法 /井上宜裕・野澤 充・徳永 元・冨川雅満
民法 /末川民事法研究会=川上生馬・大原寛史・吉村顕真・足立文美
商法 /古川朋雄・熊代拓馬・濱村実子・今川嘉文・木村健登
労働法/水島郁子・地神亮佑・稲谷信行・松井有美
民訴法/酒井博行・稻垣美穂子・上向輝宜・張子弦
刑訴法/黒澤 睦・守田智保子
経済法/田平 恵
◆法律時報 論文投稿・審査規程
| ◇制度の目的・趣旨 この制度は、法学研究の諸領域において活躍が期待される若手研究者の業績を厳正な基準の下に審査し、一定の水準と内容を持ち、本誌に掲載することがふさわしいと判断されたものに発表の機会を提供することによって、法学研究の発展に寄与することを目的とする。 |
1 投稿原稿の種類等
投稿できる原稿は、法学に関する未発表の日本語による学術論文で、他誌への掲載予定のないものに限る。ただし、紀要等で発表した学術論文で、論点を絞って再編成した論文については、投稿を認める。
2 投稿資格
大学院博士課程在学者(いわゆるオーバー・ドクターを含む)、大学もしくは短期大学の助教または日本学術振興会研究員に限り投稿することができる。ただし、法律時報編集委員会(以下「編集委員会」という)が投稿を特に認める場合は、この限りでない。
3 原稿の執筆要領
(1) 原稿は横書きとする。
(2) 分量は、1万4,000字以内とする。
(3) 図表は大きさに応じて上記の分量に算入する。
(4) 本文中の見出しは、1、(1)、(a)の順とする。
(5) 査読にあたっての匿名性を維持するため、自己の既発表論文等の引用にあたっては、「拙稿」「拙著」等による表示は避け、氏名を用いる。
(6) 注は、(1)(2)…の記号で本文該当箇所に明示し、本文の後に一括記載するか脚注とする。
4 原稿提出
(1) 原稿には下記の事項を記載した表紙を添付しなければならない。原稿自体には、氏名等を記載してはならない。
a 投稿者の氏名。
b 表題および英文タイトル。
c 投稿者の住所、電話番号およびEメール・アドレス。
d 投稿者の略歴。
e 投稿論文の分野。
(2) 原稿には、目次および400字以内の要旨を必ず添付する。
(3) 上記(1)(2)を3部郵送し、同時に各データをEメール添付ファイルで送信し、提出する。
(4) 既発表の論文等と重複する部分を含む論文の場合には、当該既発表論文等を三部添付しなければならない。
(5) 審査料は徴収しない。
(6) 送付先は下記の通りである。
〒170-8474 東京都豊島区南大塚3-12-4 日本評論社法律時報編集部論文審査係
E-mail: jihou★nippyo.co.jp(★を@に換えてください)
5 審 査
(1) 提出された原稿は、本誌への掲載にふさわしい水準・内容であるかどうか、総合的に審査される。
審査の際の主要な観点を例示すれば次の通りである。
a 法学研究への新たな貢献があること。
b 論旨が明晰であること。
c 研究方法が妥当であること。
d 表題、用語、文献引用など、表現が適切であること。
(2) 原稿の審査のため、投稿1件につき2名の者に査読を委嘱する。
ただし、本誌の趣旨に合致しないものについては、査読に付することなく不採用とすることがある。
(3) 査読者は、編集委員会の推挙により決定される。
(4) 査読者2名の査読結果に基づき、編集委員会が採否を決定する。
(5) 投稿者には採否の結果のみを通知する。
(6) 採用と決定した論文につき、内容の一層の充実をはかるため投稿者に補正を要請する場合がある。
6 その他
(1) 論文の掲載にあたり、当該論文が本制度による審査を経たものであることを誌面に表示する。
(2) 投稿者による校正は1回のみとする。校正は、誤植の訂正程度に限る。内容の訂正、変更は認めない。
(3) 原稿料は支払わない。
(4) 原稿は返却しない。
(5) 論文の掲載後、他の雑誌もしくは書籍または電子媒体等に収録する場合には、日本評論社の許諾を受けることを要する。
※2019年10月号改訂