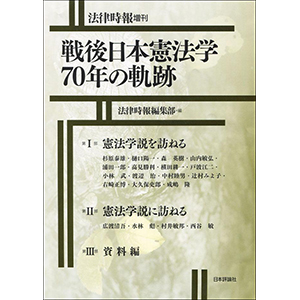法律時報 編集部ブログ 今月の最新記事
◆2025年2月号 日本社会のDXと法<好評発売中!>
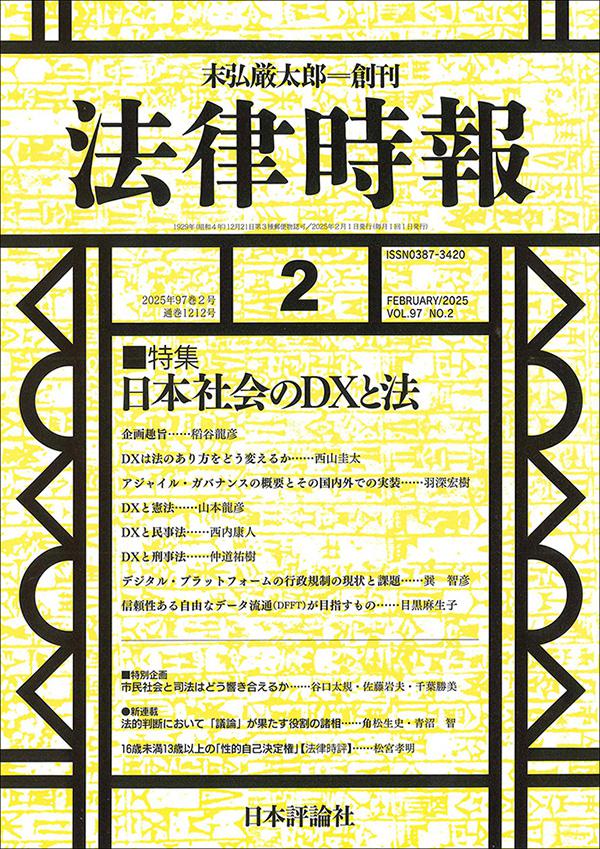
|
企画趣旨法と経済学の分野で著名な、元シカゴ大学教授かつ第7巡回区連邦控訴審裁判所判事のイースターブルックは、「サイバースペースと馬の法」と題された1996年のシカゴ大学法科大学院での講演において、「法と○○」と呼ばれる領域は、法全体を照らし出すような主題に限られるべきだと述べた。加えて … (本誌より抜粋/本文内容一部参照できます!) |
——2025年2月号目次——
DXは法のあり方をどう変えるか――ガバナンス・イノベーション再論 … 西山圭太
アジャイル・ガバナンスの概要とその国内外での実装――AI規制を題材に … 羽深宏樹
DXと憲法――ハイブリッド型意思決定のなかの「人間」 … 山本龍彦
DXと民事法――消滅・発生構成と技術的条件の果たす役割 … 西内康人
DXと刑事法――刑法学が向き合うべき課題 … 仲道祐樹
デジタル・プラットフォームの行政規制の現状と課題――「DXと行政法」の一幕として … 巽 智彦
信頼性ある自由なデータ流通(DFFT)が目指すもの――国際データガバナンスに向けた序論 … 目黒麻生子
[基調報告]公共フォーラムとしての公共訴訟と応答的司法 … 佐藤岩夫
[基調報告]市民の公共性を高めるための司法の応答 … 千葉勝美
[対談]市民社会と司法はどう響き合えるか … 佐藤岩夫・千葉勝美・谷口太規(司会)
NEW●法的判断において「議論」が果たす役割の諸相――法学と議論学との協働・1
企画趣旨 … 角松生史
議論レトリックと法的フィクション … 青沼 智
●メタ「法学入門」 4
ディシプリン … 小粥太郎
●憲法と家族法の交錯・2
同性婚訴訟・管見――第一次東京訴訟を手掛かりとして … 渡辺康行
●行政法学のリ・デザイン――二元的思考を超えて・13-1
人と物の「はざま」(上)――物の法の基底性と行政法体系の「残り半分」 … 土井 翼
●拘禁刑時代の施設内処遇・4
行刑改革会議提言と名古屋刑務所第三者委員会提言 … 田鎖麻衣子
●著作権法と刑法の語らい・19
著作権侵害に対する刑罰規定の立法論――著作権侵害は絶対的に抑止しなければならないのか … 前田 健
◆2025年1月号 デジタルプラットフォーム時代の国家管轄権<好評発売中!>
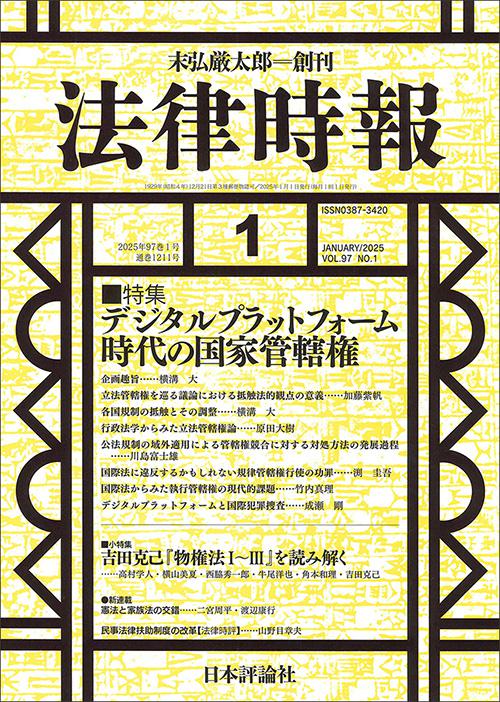
|
企画趣旨デジタルプラットフォームの多様なビジネスモデルが及ぽす社会的・経済的影響への対応として、各国はデジタルプラットフォームに対する規制を強めている。我が国でも、特定デジタルプラットフォーム提供者に情報開示・報告義務を課す、2021年2月1日に施行された … (本誌より抜粋/本文内容一部参照できます!) |
——2025年1月号目次——
立法管轄権を巡る議論における抵触法的観点の意義 … 加藤紫帆
各国規制の抵触とその調整――個人データ保護規制を題材として … 横溝 大
行政法学からみた立法管轄権論 … 原田大樹
公法規制の域外適用による管轄権競合に対する対処方法の発展過程――デジタルプラットフォーム事業者規制における問題状況への1つの視座 … 川島富士雄
国際法に違反するかもしれない規律管轄権行使の功罪――米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)のカナダ法へのインパクトを素材とした若干の考察 … 渕 圭吾
国際法からみた執行管轄権の現代的課題 … 竹内真理
デジタルプラットフォームと国際犯罪捜査――電磁的記録提供命令の導入を見据えて … 成瀬 剛
企画趣旨 … 高村学人
「財の法」としての物権法――吉田克己『物権法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』を読む … 横山美夏
過少利用時代から読み解く「財の法」の理論体系 … 高村学人
共同所有の「階層的法構造」と権限および権能 … 西脇秀一郎
吉田「占有」論ノート(吉田克己『物権法Ⅲ』)――占有概念の再検討のために … 牛尾洋也
「財の法・人の法」の理論体系と情報法 … 角本和理
リプライ … 吉田克己
――コンジョイント実験を用いた分析 … 森田 果・尾野嘉邦
●新連載憲法と家族法の交錯・1
連載開始にあたって … 二宮周平・渡辺康行
民法における「人格」と憲法13条「個人の尊重」との相互関連性 … 二宮周平
●メタ「法学入門」 3
法の中心? … 小粥太郎
●幻の創文社版『憲法綱要』とその批判的検討・21
「憲法」と「立憲主義」の間――樋口憲法学の構造に関する一視角 … 林 知更
●行政法学のリ・デザイン――二元的思考を超えて・12-2
行政法学と行政実務のはざま(下) … 平田彩子
●拘禁刑時代の施設内処遇・3
刑事施設運営の現在地――拘禁刑導入によるジレンマと課題 … 中島 学
●著作権法と刑法の語らい・19
著作権等侵害罪と違法性の意識――民事訴訟係属中の侵害継続に対する責任評価のあり方 … 遠藤聡太
◆法律時報増刊
◆判例回顧と展望 2024年度版(法律時報臨時増刊)
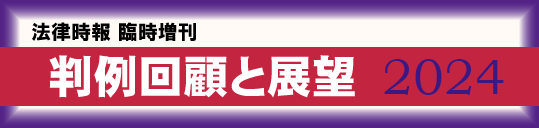
≪2025年6月上旬 発売≫
2022年度に文献掲載された重要判例を法分野別に整理し、その意義と位置づけを簡潔明快にコメント。毎年好評の判例特集号最新版。
—— 目次 ——
憲法 /金澤 誠・黒澤修一郎・横堀あき・内藤 陽・大串倫一・齊藤正彰
行政法/佐伯彰洋・小川一茂・重本達哉・近藤卓也
刑法 /井上宜裕・野澤 充・徳永 元・冨川雅満
民法 /末川民事法研究会=川上生馬・大原寛史・吉村顕真・足立文美
商法 /古川朋雄・熊代拓馬・濱村実子・今川嘉文・木村健登
労働法/水島郁子・地神亮佑・稲谷信行・松井有美
民訴法/酒井博行・稻垣美穂子・上向輝宜・張子弦
刑訴法/黒澤 睦・守田智保子
経済法/田平 恵
◆法律時報 論文投稿・審査規程
| ◇制度の目的・趣旨 この制度は、法学研究の諸領域において活躍が期待される若手研究者の業績を厳正な基準の下に審査し、一定の水準と内容を持ち、本誌に掲載することがふさわしいと判断されたものに発表の機会を提供することによって、法学研究の発展に寄与することを目的とする。 |
1 投稿原稿の種類等
投稿できる原稿は、法学に関する未発表の日本語による学術論文で、他誌への掲載予定のないものに限る。ただし、紀要等で発表した学術論文で、論点を絞って再編成した論文については、投稿を認める。
2 投稿資格
大学院博士課程在学者(いわゆるオーバー・ドクターを含む)、大学もしくは短期大学の助教または日本学術振興会研究員に限り投稿することができる。ただし、法律時報編集委員会(以下「編集委員会」という)が投稿を特に認める場合は、この限りでない。
3 原稿の執筆要領
(1) 原稿は横書きとする。
(2) 分量は、1万4,000字以内とする。
(3) 図表は大きさに応じて上記の分量に算入する。
(4) 本文中の見出しは、1、(1)、(a)の順とする。
(5) 査読にあたっての匿名性を維持するため、自己の既発表論文等の引用にあたっては、「拙稿」「拙著」等による表示は避け、氏名を用いる。
(6) 注は、(1)(2)…の記号で本文該当箇所に明示し、本文の後に一括記載するか脚注とする。
4 原稿提出
(1) 原稿には下記の事項を記載した表紙を添付しなければならない。原稿自体には、氏名等を記載してはならない。
a 投稿者の氏名。
b 表題および英文タイトル。
c 投稿者の住所、電話番号およびEメール・アドレス。
d 投稿者の略歴。
e 投稿論文の分野。
(2) 原稿には、目次および400字以内の要旨を必ず添付する。
(3) 上記(1)(2)を3部郵送し、同時に各データをEメール添付ファイルで送信し、提出する。
(4) 既発表の論文等と重複する部分を含む論文の場合には、当該既発表論文等を三部添付しなければならない。
(5) 審査料は徴収しない。
(6) 送付先は下記の通りである。
〒170-8474 東京都豊島区南大塚3-12-4 日本評論社法律時報編集部論文審査係
E-mail: jihou★nippyo.co.jp(★を@に換えてください)
5 審 査
(1) 提出された原稿は、本誌への掲載にふさわしい水準・内容であるかどうか、総合的に審査される。
審査の際の主要な観点を例示すれば次の通りである。
a 法学研究への新たな貢献があること。
b 論旨が明晰であること。
c 研究方法が妥当であること。
d 表題、用語、文献引用など、表現が適切であること。
(2) 原稿の審査のため、投稿1件につき2名の者に査読を委嘱する。
ただし、本誌の趣旨に合致しないものについては、査読に付することなく不採用とすることがある。
(3) 査読者は、編集委員会の推挙により決定される。
(4) 査読者2名の査読結果に基づき、編集委員会が採否を決定する。
(5) 投稿者には採否の結果のみを通知する。
(6) 採用と決定した論文につき、内容の一層の充実をはかるため投稿者に補正を要請する場合がある。
6 その他
(1) 論文の掲載にあたり、当該論文が本制度による審査を経たものであることを誌面に表示する。
(2) 投稿者による校正は1回のみとする。校正は、誤植の訂正程度に限る。内容の訂正、変更は認めない。
(3) 原稿料は支払わない。
(4) 原稿は返却しない。
(5) 論文の掲載後、他の雑誌もしくは書籍または電子媒体等に収録する場合には、日本評論社の許諾を受けることを要する。
※2019年10月号改訂