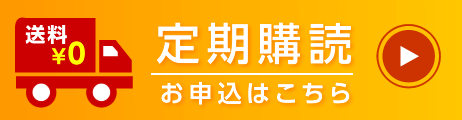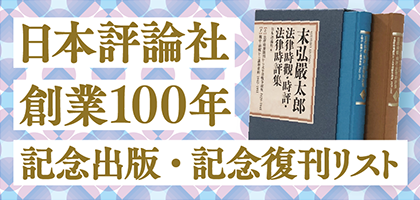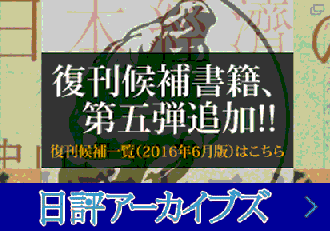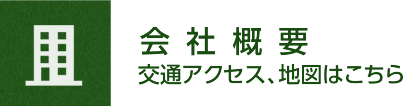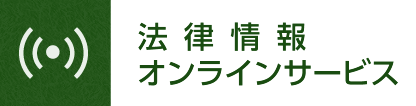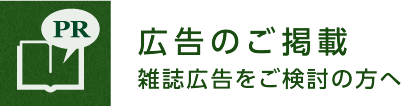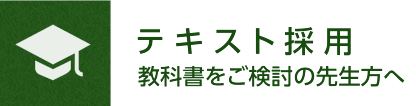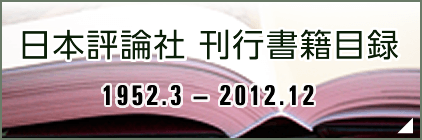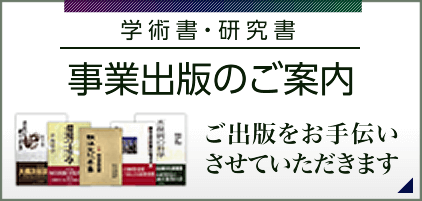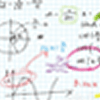新刊情報 一覧
【新刊】『代数学のレッスン』本日、4月5日発売!
【電子書籍新刊】『発明の経済学』本日4月4日より配信開始!
Kindle版の配信を4月4日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)
(長岡貞男/著)
発明の創造過程やその商業化過程で何が起きているのか。理論と実証のギャップを埋め、イノベーションを高める要因を分析する。【プリントレプリカ版】
【刊行予告】『司法試験・予備試験 短答式過去問題集 刑法[第2版]』他1冊、4月6日発売!
(伊藤 真/監修・伊藤塾/編)《伊藤塾 合格セレクション》
司法試験・予備試験の短答式試験過去問の中から合格のために解けなければならない問題を厳選! 令和3年度の問題までカバー。
(明海大学不動産学部創設30周年記念出版会/編)
近年の不動産学が対象とする実社会に発生している諸問題とその解決策を、法学、工学、経済学、経営学の各分野から探求する。
【刊行予告】『そだちの科学 No.38』(2022年4月号)、4月6日発売!
特集=子ども臨床の課題と難題
滝川一廣・杉山登志郎・田中康雄・村上伸治・土屋賢治/編
子ども臨床あるいは児童青年精神医学の今日的課題・難題について、本誌編集人をはじめ、この分野の専門家が振り返る。
【新刊】『初歩からはじめる物権法』他1冊、本日4月4日発売!
(山野目章夫/著)
初学者に向け、豊富な例題を交えながら、物権法の基本を明快に解説する。社会や経済、実務を踏まえた大きな視野で、民法を繙く。
(伊藤 真/監修・伊藤塾/編)《伊藤塾 合格セレクション》
条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に立ち向かうツールとしての憲法理論を追求する教科書の第3版。
【電子書籍新刊】『すべての人の天文学』他6冊、4月1日より配信開始!
Kindle版の配信を4月1日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)
(岡村定矩・芝井 広/監修、縣 秀彦/編著)
文科系や教員養成系の大学生に、最低限知ってほしい「天文学のリテラシー」を解説。中学校までの知識で、天文学がわかる。【プリントレプリカ版】
(中島 宏・宮木康博・笹倉香奈/著)
刑事訴訟法の基本をコンパクトに解説。学習の基礎を体得することに重点を置きつつ、わかりやすい解説で学習をサポートする。【プリントレプリカ版】
(鈴木 賢/著)
台湾で同性婚を認める法律が成立するまでのLGBT運動、政治過程、法の内容を分析し、法施行後の台湾社会の変化と課題を考察する。
(原田昌和・寺川 永・吉永一行/著)
相続分野や所有者不明土地に関わる民法改正などを反映しつつ、さらに分かりやすい記述へのアップデートを図った定番の教科書。【プリントレプリカ版】
 『社会に最先端の数学が求められるワケ(1) 新しい数学と産業の協奏』
『社会に最先端の数学が求められるワケ(1) 新しい数学と産業の協奏』
(国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター(JST/CRDS)・高島洋典・吉脇理雄/編、岡本健太郎・松江 要/著)
社会のさまざまな問題を解決するために、どのような数学が必要なのか。第1巻では数学と産業界で交差する研究を紹介する。【プリントレプリカ版】
 『社会に最先端の数学が求められるワケ(2) データ分析と数学の可能性』
『社会に最先端の数学が求められるワケ(2) データ分析と数学の可能性』
(国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター(JST/CRDS)・高島洋典・吉脇理雄/編、杉山真吾・横山俊一/著)
社会を埋め尽くす膨大なデータに対し、数学はどのように役立ち活躍できるのか。第2巻ではデータ社会に挑む数学を紹介する。【プリントレプリカ版】
(梶原 健/著)
線形代数の基本中の基本,行列と行列式について,理解すべきポイントを明示し,多くの例題や図式を通して丁寧に学べる一冊。
【新刊】『憲法講義[第3版]』他1冊、本日4月1日発売!
(本 秀紀/編)
条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に立ち向かうツールとしての憲法理論を追求する教科書の第3版。
(田中雅子/著)
民主主義体制下、有権者に反発を受けやすい政策はいかにして成立に至るのか。消費税を題材に政権構造の果たす重要性を論じる。
【刊行予告】『初歩からはじめる物権法』他1冊、4月4日発売!
(山野目章夫/著)
初学者に向け、豊富な例題を交えながら、物権法の基本を明快に解説する。社会や経済、実務を踏まえた大きな視野で、民法を繙く。
(伊藤 真/監修・伊藤塾/編)《伊藤塾 合格セレクション》
条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に立ち向かうツールとしての憲法理論を追求する教科書の第3版。
【新刊】『公認心理師試験の問題と解説2022』他2冊、本日3月31日発売!
(こころの科学増刊編集部/編)
第4回試験の全問解説と最新版出題基準の分析を持ち運びに便利なサイズでスラスラ読める! 第5回試験に向けた勉強に活かそう。
(秋山靖浩・伊藤栄寿・大場浩之・水津太郎/著)
相続法分野や所有者不明土地に関わる民法改正に対応した第3版。教材に、独習に最適な教科書。
(中島 宏・宮木康博・笹倉香奈/著)
刑事訴訟法の基本をコンパクトに解説。学習の基礎を体得することに重点を置きつつ、わかりやすい解説で学習をサポートする。
【刊行予告】『憲法講義[第3版]』他1冊、4月1日発売!
(本 秀紀/編)
条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に立ち向かうツールとしての憲法理論を追求する教科書の第3版。
(田中雅子/著)
民主主義体制下、有権者に反発を受けやすい政策はいかにして成立に至るのか。消費税を題材に政権構造の果たす重要性を論じる。



![『司法試験・予備試験 短答式過去問題集 刑法[第2版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52645-105x150.jpg)



![『司法試験・予備試験 短答式過去問題集 憲法[第2版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52643-106x150.jpg)



![『民法総則[第2版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/80694-105x150.jpg)

![『憲法講義[第3版] 』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52563_obi-1-105x150.jpg)


![『物権法[第3版]』《日評ベーシック・シリーズ》](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/80696_obi-105x150.jpg)