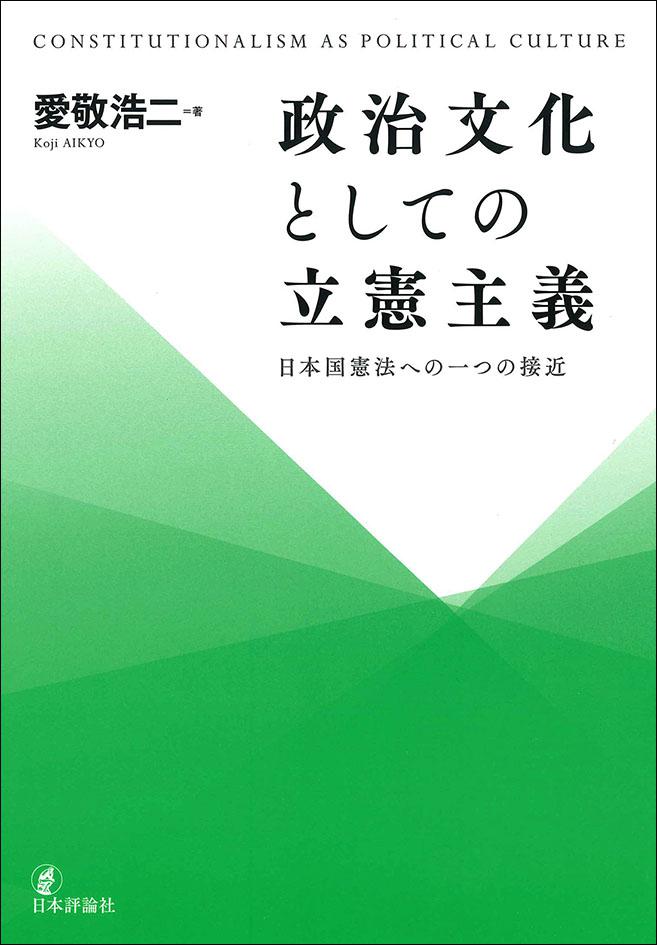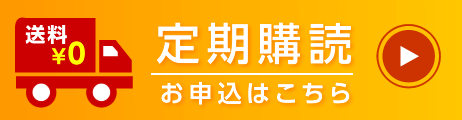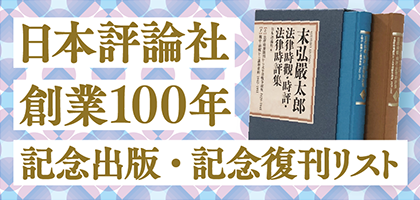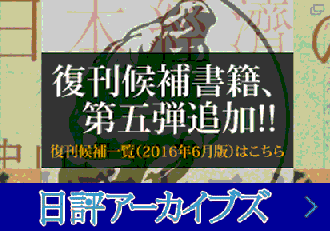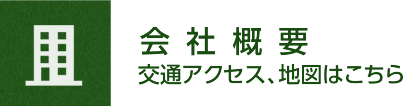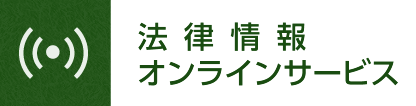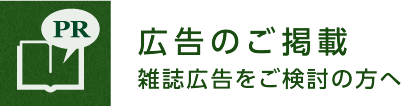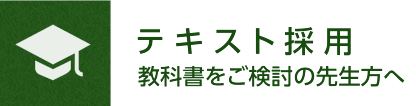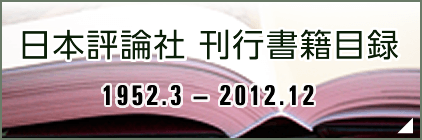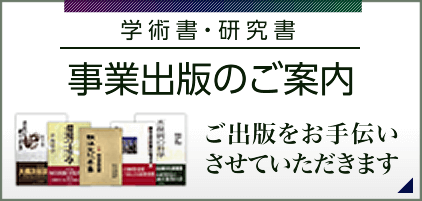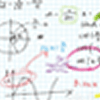書籍詳細:政治文化としての立憲主義
政治文化としての立憲主義 日本国憲法への一つの接近
- 紙の書籍
- 電子書籍
定価:税込 8,140円(本体価格 7,400円)
紙の書籍・POD・アーカイブズの価格を表示しています。
電子書籍の価格は各ネット書店でご確認ください。
電子書籍の価格は各ネット書店でご確認ください。
在庫あり
紙の書籍のご購入
内容紹介
近代立憲主義の起源と展開を憲法思想・憲法理論・比較憲法の3つの観点を総合して研究する著者の立憲主義研究をまとめた書。
目次
序 章 主題と副題をめぐる若干の回顧
Ⅰ 「政治文化としての立憲主義」という主題に寄せて
Ⅱ 「日本国憲法への一つの接近」という副題に寄せて
______________________________
第Ⅰ部 「政治文化」としての法の支配と立憲主義
______________________________
第1章 「法の支配」再考――憲法学の観点から
Ⅰ 「法の支配」は無条件の善?
Ⅱ 「法の支配」と「法治主義」
Ⅲ 「法の支配」と現代イギリス憲法学
Ⅳ 二つの「法の支配」論――佐藤とアラン
Ⅴ 政治道徳哲学への禁欲とその帰結
Ⅵ 改めて「法の支配」の多義性について
第2章 戦後日本公法学と法の支配
はじめに
Ⅰ 法の支配の政治文化――日米の対照性
Ⅱ 戦後公法学の出発と法の支配
Ⅲ 「厚い法の支配」と「薄い法の支配」
Ⅳ 「法の支配」の再構築
Ⅴ 日本における法の支配の価値
第3章 立憲主義と民主主義
Ⅰ 立憲主義の復権と民主主義からの反撃
Ⅱ 「立憲主義と民主主義」という問題設定の意味
Ⅲ 「プロセス的司法審査理論」とその論拠
Ⅳ 多元主義と共和主義――どんな民主主義か?
結びに代えて
第4章 ジェレミー・ウォルドロンの違憲審査制批判について
はじめに
Ⅰ ウォルドロンの議論は「人民立憲主義」か?
Ⅱ 「ハイブリッド型」の人権保障システム
Ⅲ ウォルドロンの違憲審査制批判の概要とその特徴
Ⅳ ファロンによる違憲審査制擁護論とその問題点
Ⅴ タシュネットによる論争の評価とその意義
Ⅵ 憲法理論の二つのレベルとその役割
結びに代えて
第5章 政治文化としての立憲主義
――J・ウォルドロンの憲法理論に関する一考察
Ⅰ 盟友か、論敵か――ウォルドロンとサイドマン
Ⅱ 憲法理論の固有性と相対性
Ⅲ サイドマンの「憲法不服従論」とウォルドロンの批判
Ⅳ ウォルドロンの違憲審査制批判の特徴と問題意識
Ⅴ 「政治文化としての立憲主義」と憲法制度・憲法運用
結びに代えて
______________________________
第Ⅱ部 基本的人権論への接近
______________________________
第6章 近代人権論と現代人権論
――「人権の主体」という観点から
Ⅰ 人権論における「近代」と「現代」
Ⅱ 人権の国際化と現代人権論
Ⅲ 限定的人権論と拡張的人権論
Ⅳ 限定的人権論の制度的前提
結びに代えて
第7章 「憲法的思惟」と国際人権の間
――蟻川恒正『尊厳と身分』を読む
Ⅰ 憲法的思惟と「日本」という問題
Ⅱ 『尊厳と身分』の内容構成
Ⅲ 「尊厳と身分」論文を読む
Ⅳ 「違憲審査制批判者ウォルドロン」という問題意識の乏しさ
Ⅴ 「国際人権法の不在」という問題
Ⅵ まとめとお詫び
第8章 基本権の私人間効力論
――憲法・民法問題の観点から憲法学の課題を探る
Ⅰ 私人間効力論の活況と本章の問題意識
Ⅱ 憲法審査の制度設計と私人間効力論
Ⅲ 「市民社会論のルネッサンス」と憲法・民法問題
Ⅳ 現代憲法への転換と私的自治の現代的変容
Ⅴ 民法2条論における憲法学・民法学の交差と協働
Ⅵ 私人間効力論の課題に関する若干の問題提起――結びに代えて
第9章 憲法と独占禁止法――序論的考察
Ⅰ 「二つの憲法」の現在
Ⅱ 憲法と独禁法――いくつかの論点
Ⅲ 規制目的二分論とその問題点
Ⅳ 規制緩和論と規制目的二分論
Ⅴ 規制目的二分論と民主政
Ⅵ 憲法 vs. 独禁法?――新聞再販制度をめぐって
Ⅶ 憲法から考える新聞再販制度
結びに代えて
第10章 憲法学はなぜリバタリアニズムをシリアスに受け止めないのか?
Ⅰ 憲法学とリバタリアニズム
Ⅱ 政治道徳哲学と実定憲法
Ⅲ 経済的自由の憲法理論
結びに代えて
補論1 原発問題における学問の自由と知る権利
Ⅰ 憲法学も社会的意味を問われている
Ⅱ 原発研究における学問の不自由
Ⅲ 「原子力ムラ」と「安全神話」
Ⅳ 原発問題における情報流通の不自由
Ⅴ 「学問の自由」と「知る権利」で対応可能か?
Ⅵ 福島第一原発事故とリスク認知の変容
Ⅶ 「安全性のパラドクス」と専門家の権威のゆらぎ
Ⅷ 原発論議の熟議民主主義化に向けて
Ⅸ 原発研究のこれから――「人間の復興」に向けて
補論2 営業「自粛」と憲法
Ⅰ 感染拡大防止対策としての「自粛」要請
Ⅱ 補償なければ禁止なし?
Ⅲ 「自由」の意味を問い直す
Ⅳ 営業「自粛」と損失補償
______________________________
第Ⅲ部 統治機構論・憲法政治への接近
______________________________
第11章 「裁判官の良心」に関する一考察
Ⅰ 「裁判官の良心」論の再活性化?
Ⅱ 「裁判官の良心」と裁判官
Ⅲ 「裁判官の良心」に関する学説状況
Ⅳ 長谷部恭男の「裁判官の良心」論
Ⅴ 長谷部「裁判官の良心」論の理論的基礎
Ⅵ 長谷部「裁判官の良心論」の転回?
Ⅶ 長谷部「裁判官の良心」論と裁判官
結びに代えて
第12章 「裁判官の良心」と裁判官
――憲法理論的考察に向けて
Ⅰ 本章の課題
Ⅱ 裁判官にとっての「裁判官の良心」
Ⅲ 裁判官の良心論の普遍性と固有性
Ⅳ 「言説上の裁判官」と「裁判官の言説」
Ⅴ 裁判官の良心論の更なる活性化に向けて
第13章 「統治行為」緒論の批判的考察
Ⅰ 砂川判決と統治行為論
Ⅱ 奥平康弘「『統治行為』理論の批判的考察」再読
Ⅲ 「統治行為」緒論と比較憲法
Ⅳ 「大文字の政治」の司法問題化と「統治行為」緒論
Ⅴ 統治行為・緊急事態・法の支配・憲法9条
結びに代えて
第14章 国家緊急権論と立憲主義
Ⅰ 本章の問題関心
Ⅱ 〈3.11〉の後で国家緊急権を論ずる意味(と無意味)
Ⅲ 拷問禁止緩和論とリベラル・イデオロギー
Ⅳ イデオロギーとしての立憲主義?
Ⅴ 国家緊急権と立憲主義の関係
Ⅵ 〈9.11〉後の国家緊急権論
Ⅶ 「側法性」と「法システムの元型」
Ⅷ オレン・グロスの「法外モデル」の検討
Ⅸ 「アンチ・シュミット」モデルとの比較
Ⅹ 森英樹による問題提起の評価――結びに代えて
第15章 改憲問題としての緊急事態条項
はじめに
Ⅰ 国家緊急権の定義と分類
Ⅱ シュミットから遠く離れて?――現代立憲民主政と国家緊急権
Ⅲ 自民党「改憲草案」の緊急事態条項
Ⅳ 自然災害と緊急事態条項
Ⅴ 「法外モデル」を論ずる意味
結びに代えて
第16章 立憲・平和主義の構想
Ⅰ 立憲平和主義の危機の中で、立憲・平和主義を再考する
Ⅱ 立憲・平和主義の「相対性」
Ⅲ 「平和主義の相対化」と憲法学説
Ⅳ 立憲主義と平和主義の関係をどう考えるか
Ⅴ 国際立憲主義と立憲・平和主義
結びに代えて
第17章 憲法9条訴訟と市民社会
――憲法学者の立場から
Ⅰ 「市民社会の新たな胎動」と憲法9条訴訟――本章の課題
Ⅱ 本章の基底にある問題意識――奥平康弘と道場親信の問題提起
Ⅲ 憲法9条訴訟とは何か
Ⅳ イラク派兵差止訴訟という経験
Ⅴ 安保法制違憲訴訟という課題
Ⅵ 憲法9条訴訟の可能性――結びに代えて
終 章 「生ける憲法」という思想と方法
――奥平憲法学から学んだこと
Ⅰ 奥平憲法学における「生ける憲法」論――その一貫性
Ⅱ 「生ける憲法」とコモン・ロー立憲主義
Ⅲ 「成功の物語」としてのコモン・ロー立憲主義の問題点
Ⅳ 裁判官が語るコモン・ロー立憲主義の問題点
Ⅴ 希望としての「連戦連敗」論
あとがき